名誉院長
唐川 正洋からかわ まさひろ
| 専門分野 |
|
|---|---|
| 認定資格 |
|

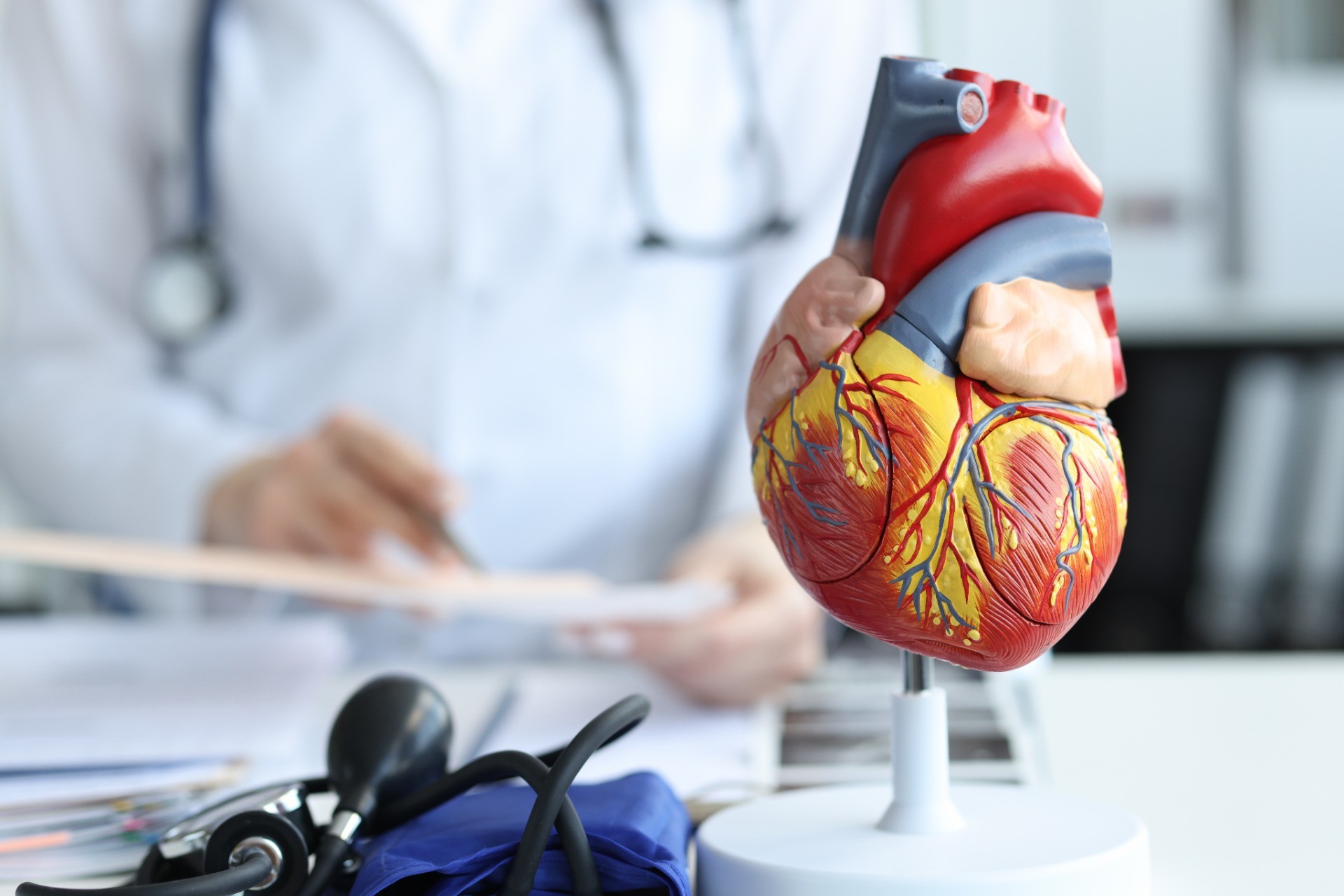
当院は1996年4月に循環器内科を開設し、現在は8名の循環器常勤医と非常勤医が診療にあたっています。当科では主に心臓病と血管病の診療を担当しており、これらの疾患は急性期の適切な処置が不可欠です。そのため、私たちは24時間365日、休日や夜間の待機体制を整え対応しています。皆さまの安心と安全を最優先に考え、近隣医療機関からの要請にも素早くかつ円滑に対応するため、積極的にドクターカーを活用しています。 私たちは皆さまとの信頼関係を築きながら、最新の診療技術を提供し、個別の治療計画を立案しています。一人ひとりのニーズに合わせた最適な治療を行い、病気と真摯に向き合い、みなさまの健康を支えていきます。
当科の特徴は、医師全員が連携して患者さんの状態を把握し、迅速かつ適切な治療を提供しています。また、看護師や他のスタッフもチームで協力し、患者さんの要望を尊重して心のこもったケアを行っています。これにより、患者さんとその家族が安心して治療を受けられる環境を整えています。
循環器内科では、心臓や血管に関連するさまざまな疾患に対する診療を行っています。主な対象疾患には以下が含まれます。
など
心臓リハビリテーションは、単なる運動療法ではなく、医師、看護師、理学療法士、薬剤師、管理栄養士などがチームとなって患者さんと協力し、心臓病や血管病にアプローチするプログラムです。対象は虚血性心疾患、心不全、閉塞性動脈硬化症、弁置換術後などで、入院中だけでなく外来通院でも行われます。中核となるのは運動療法で、心肺運動負荷検査で評価を行い、安全で効果的な運動療法を提供します。運動は健康の改善や寿命延長につながりますが、効果を実感するには継続が大切です。詳細は担当医や循環器内科外来に問い合わせてください。
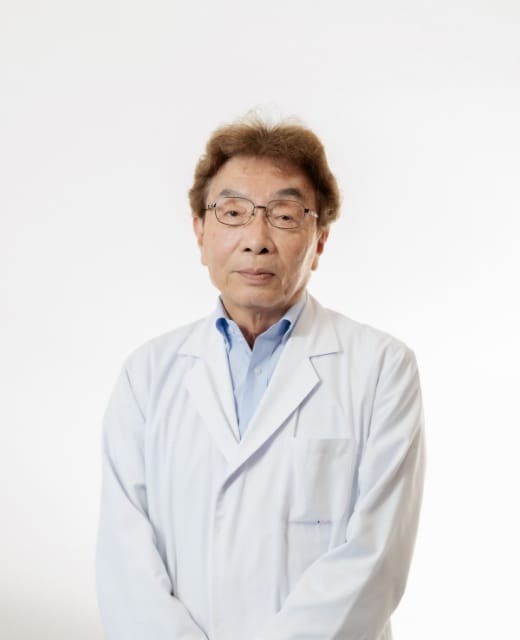
名誉院長
唐川 正洋からかわ まさひろ
| 専門分野 |
|
|---|---|
| 認定資格 |
|
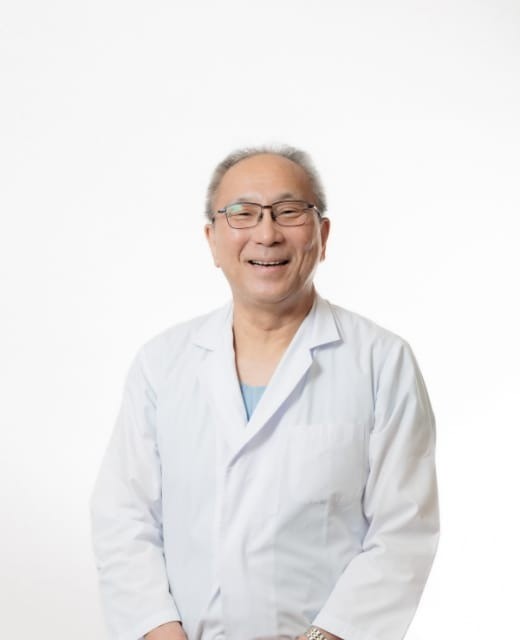
参与
吉長 正博よしなが まさひろ
| 専門分野 |
|
|---|

主任部長
山治 憲司やまじ けんじ
| 専門分野 |
|
|---|---|
| 認定資格 |
|
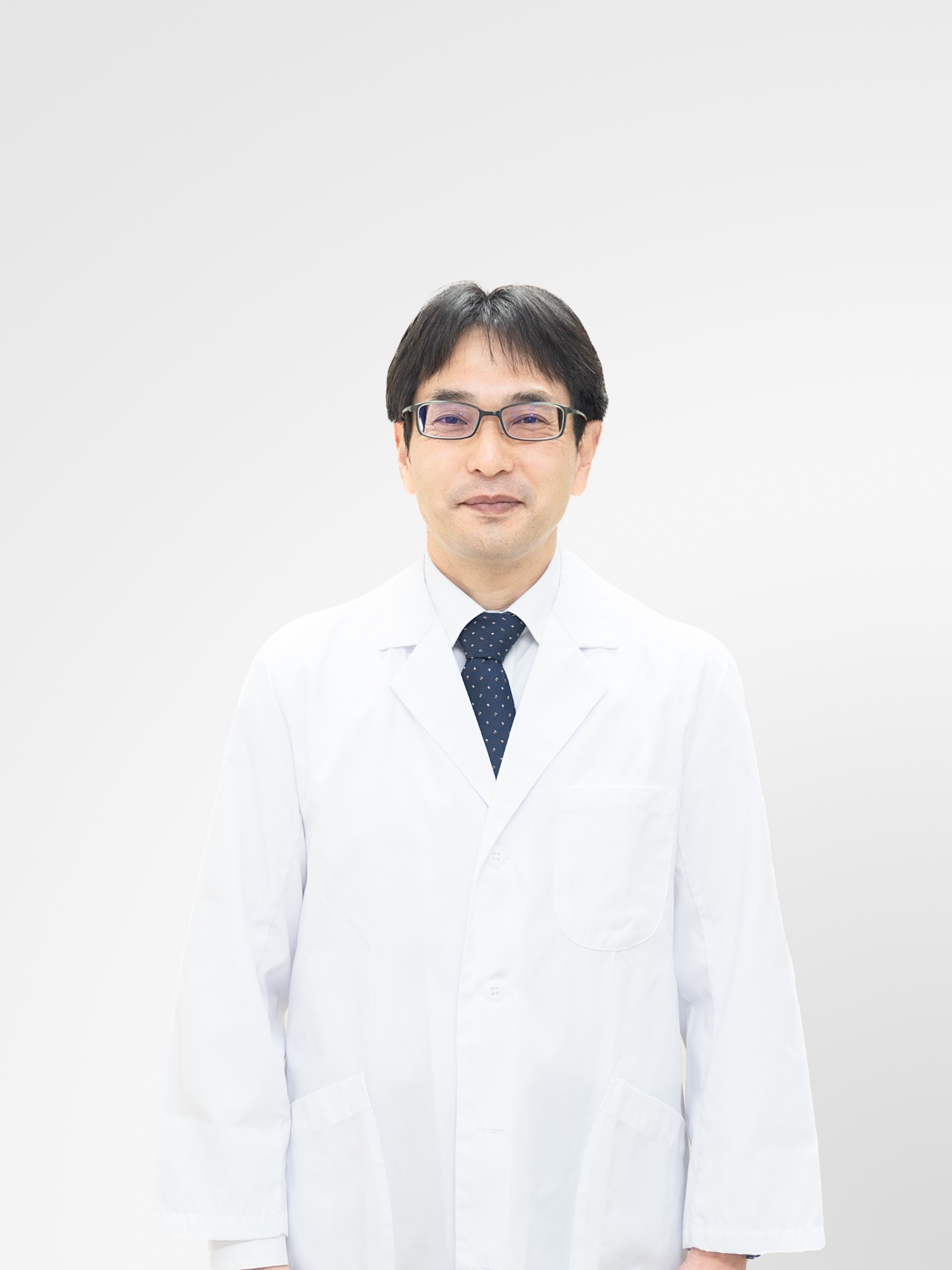
部長
中川 英一郎なかがわ えいいちろう
| 専門分野 |
|
|---|---|
| 認定資格 |
|

副医長
髙橋 直也たかはし なおや
| 専門分野 |
(冠動脈インターベンション)
|
|---|---|
| 認定資格 |
|

副医長
藤原 宏太ふじはら こうた
| 専門分野 |
|
|---|---|
| 認定資格 |
|

副医長
布川 裕人ふかわ ゆうと
| 専門分野 |
|
|---|---|
| 認定資格 |
|
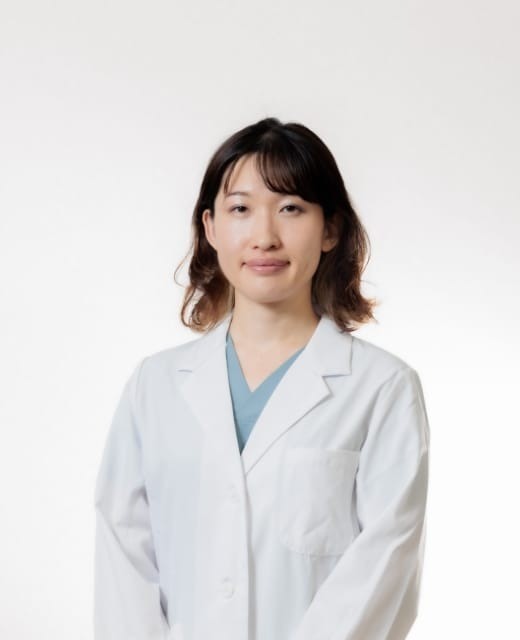
内科専攻医
加古 真由かこ まゆ
| 専門分野 |
|
|---|---|
| 認定資格 |
|

内科専攻医
上杉 将功うえすぎ まさかつ
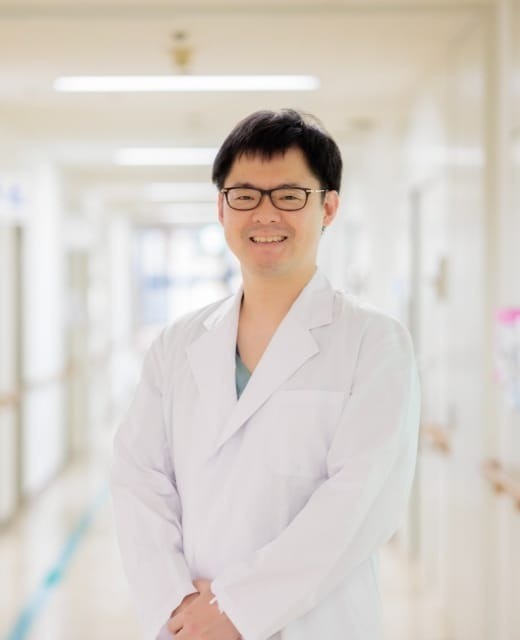
非常勤医師
西浦 崇にしうら たかし
| 専門分野 |
|
|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1診 (予約) |
髙橋 | 吉長 | 布川 | 吉長 | 藤原 | 交代制 (初診) |
| 2診 (新患・紹介) |
中川 | 西浦 | 末吉 | 松木 | 山治 | - | |
| 3診 | - | 唐川 | - | 加古 | - | - | |
| 共用診察室 |
ペースメーカー外来 |
- | - | 山治 (下肢閉塞性動脈硬化症外来) (予約制) |
ペースメーカー外来 (第2,4週) |
- | |
| 午後 | 1診 (予約) |
髙橋 | 吉長 | 布川 | - | - | - |
| 2診 (予約) |
中川 | 西浦 | 末吉 | 松木 | 山治 | - | |
| 3診 (予約) |
- | - | - | 加古 | - | - | |
| 検査 | 心エコー 心筋シンチ 心臓カテーテル |
心エコー 運動負荷 心臓カテーテル |
心エコー 心臓カテーテル |
心エコー 心臓カテーテル |
心エコー 心臓カテーテル |
- | |
アブレーション外来は完全予約制(火・木・金)となっております。
下肢閉塞性動脈硬化症外来は完全予約制(木曜日午前)となっております。
※案内パンフレットはこちら
下肢閉塞性動脈硬化症外来・アブレーション外来ご紹介の患者さんにつきましては地域連携課(直通電話:06-6552-0390)までご連絡下さい。
| 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|
| 心臓超音波検査 | 3346件 | 3377件 |
| 血管超音波検査 | 878件 | 955件 |
| 心臓核医学検査 | 217件 | 193件 |
| 24時間心電図 | 454件 | 367件 |
| 冠動脈造影 | 529件 | 575件 |
| 経皮的冠動脈形成術 | 164件 | 210件 |
| 末梢動脈拡張術 | 42件 | 37件 |
| 心臓ペースメーカー、ICD、CRT | 45件 | 62件 |
| 不整脈アブレーション | 134件 | 118件 |
当院では24時間365日、循環器内科医が緊急時待機態勢を整え、夜間や休日でも循環器疾患の受け入れを行っています。また、近年はドクターカーを活用した患者受け入れも積極的に行っています。循環器疾患の疑いがある場合は、少しでも早くご連絡いただければ、迅速に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
当院では、心臓や血管に関連する多くの疾患を診療しています。例えば、心筋梗塞や狭心症、不整脈、高血圧、心不全、心臓弁膜症、動脈硬化、動脈瘤などです。
胸痛、息切れ、動悸、むくみ、失神、背中の痛みなどが一般的な症状です。また、症状が無くても健康診断で異常が見つかった場合に受診されることがあります。
胸痛は心臓疾患の典型的な症状で、締め付けられるような痛みや圧迫感を感じることがあります。狭心症では数分で軽減しますが、心筋梗塞では強い痛みが持続します。
平日は午前9時から午後5時まで、土曜日は午前9時から午後1時まで診療を行っています。下肢閉塞性動脈硬化症外来・アブレーション外来診察の問い合わせは、地域連携課(直通電話: 06-6552-0390)までご連絡ください。 夜間や休日も救急体制を整えており、循環器疾患の救急受け入れを行っています。お気軽にご相談ください。
診療科・専門外来・部門紹介